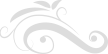世田谷区 葬儀 家族葬|葬儀・家族葬は都典礼世田谷店
"またお願いしたい"と言われる葬儀社です
葬儀業界の大手口コミサイト
世田谷区で2年連続No.1
"またお願いしたい"と言われる葬儀社です
葬儀業界の大手口コミサイト
世田谷区で2年連続No.1
- 全葬連葬祭サービス安心度調査で最高ランク受賞
- 満足度98%で、初めてでも全てお任せ!
- 創業53年、累計2万件以上の葬儀実績


葬儀社の比較に最適
ネットで簡単注文
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店の
葬儀プラン
![]() Plan
Plan ![]()
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店では、3つの葬儀プランをご用意しております。どれも、世田谷区周辺に住む方にとって最適の葬儀プランとなっております。状況やご意向によってお選びください。
世田谷区の皆さまから
選ばれる3つの理由
![]() Reason
Reason ![]()
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店が、世田谷区の皆様から支持されているのには主に3つの理由がございます。

世田谷区の葬儀で
口コミ1位*1を獲得
世田谷区の葬儀で口コミ1位を獲得しました!
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店は、東京都世田谷区を中心とした多くの方々に選んでいただいております。
*1...「葬儀の口コミ」全口コミ178件
総合評価☆4.95 獲得(2023/8時点)
創業以来2万件以上の実績
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店は創業53年、世田谷区で実績を積み上げました。
また全葬連より「全葬連葬祭サービス安心度調査」で最高ランクを受賞。


担当スタッフが
一貫してサポート
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店は、相談から葬儀終了まで、同じスタッフが担当させて頂きます。
おかげさまで世田谷区で顧客満足度は98%以上!
お客様の声
![]() Voice
Voice ![]()
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店では、葬儀を行ったお客様に対してアンケートを実施し、葬儀サービスの改善に努めています。
実際の葬儀事例とお客様の声を合わせてご紹介いたします。
斎場案内
![]()
![]()
![]()
![]()
世田谷区周辺の方々にとって、ご利用しやすい斎場をご紹介いたします。また、インターネット上の情報だけで判断せず、実際に斎場に詳しいスタッフにお聞きください。ご要望やご状況に合わせて斎場をご提案します。


代々幡斎場
控室
安置
駐車場
火葬場併設
〒151-0066
東京都渋谷区西原
2丁目42−1


桐ヶ谷斎場
控室
安置
駐車場
火葬場隣設
〒141-0031
東京都品川区西五反田
5丁目32−20


落合斎場
控室
安置
駐車場
火葬場併設
〒161-0034
東京都新宿区上落合
3丁目34−12
その他にも世田谷区周辺にはたくさんの斎場がございます。詳しくは下の斎場一覧からご覧ください。
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店が懸ける
葬儀への想い
![]()
![]()
![]()
![]()


葬儀・家族葬は都典礼世田谷店は、“真心のお手伝い”を会社の理念に、昭和46年に八王子市で創業いたしました。
東京都世田谷区に在る地域密着の小さな葬儀社でございます。
地域密着の小さな葬儀社だからこそ出来る、一つ一つのご葬儀にしっかりと時間を掛けてご遺族様に寄り添い質の高いサービスが、みなさまからのご支持そしてご満足されている事と自負しております。
ご遺族様のさまざまなご要望にも適切なご提案で丁寧に応えてまいります。
どのような事でも全てのスタッフが、親身になってお応えいたしますので、安心してお任せ下さい。
53年間の実績と信頼で『安心の葬儀』をお約束いたします。
葬儀・家族葬は都典礼世田谷店長 吉田哲也
【一級葬祭ディレクター】