ご逝去・ご危篤でお急ぎの方はもちろん![]() 些細なことでもお気軽にお電話ください
些細なことでもお気軽にお電話ください ![]()
- ボタンをタップすると電話がかかります。
ご逝去・ご危篤でお急ぎの方はもちろん![]() 些細なことでもお気軽にお電話ください
些細なことでもお気軽にお電話ください ![]()
 生花祭壇
生花祭壇 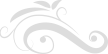
都いちょう倶楽部ご入会で
基本設営費
649,330円
20%割引
519,464円
人件費|90,200円
車両費|36,960円
付属費|11,000円

総額|787,490円

会員価格|657,624円
約13万円お得!
飲食費、会葬返礼品、香典返し、霊柩車、
マイクロバス、宗教者への謝礼等は含んでおりません。
 白木祭壇
白木祭壇 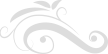
都いちょう倶楽部ご入会で
基本設営費
594,330円
30%割引
416,031円
人件費|90,200円
車両費|36,960円
付属費|11,000円

総額|732,490円

会員価格|554,191円
約18万円お得!
飲食費、会葬返礼品、香典返し、霊柩車、
マイクロバス、宗教者への謝礼等は含んでおりません。