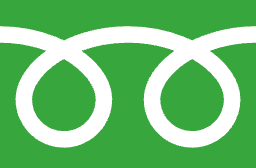ご葬儀に参列する時、お香典の不祝儀袋の書き方について悩んでしまうことはありませんか?
この記事をご覧頂ければ、正しく失礼のない表書きの書き方や渡し方がわかります。
マナーを守って、ご遺族へ失礼のないようにお渡ししましょう。
こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
香典とは?
香典はご葬儀の際に、お香や食べ物を持ち寄って助け合う相互扶助の慣習が、現代で金銭として変化したものです。
昔はお香が高価なものでした。一晩中焚き続け、煙を絶やさず道しるべとする為に大量のお香が必要だったことから、ご遺族の負担を軽くするために持ち寄っていたのです。
それが現代では、金銭を包んで参列者が持って行くのが一般的になりました。
香典の表書きの書き方
お香典を入れる袋を不祝儀袋といいます。
今はコンビニや100円ショップでも買えますので、ご葬儀に参列することが決まった時点で、薄墨の筆ペンと一緒に用意しておきましょう。
この項目では、宗教や宗派ごとに表書きの書き方についてご説明していきます。
表書きとは、袋の半分から上に記載する文言の事で、半分から下には名前を記入します。
相手によっては良く思われない場合もありますので、プリンターなどを使用せず、手書きで記入しましょう。表書きが最初から選べるように印刷されているものは、そのまま使用して問題ありません。
仏式
ご葬儀では「御霊前」「御香典」「御香料」
四十九日以降は「御仏前」「御佛前」
浄土真宗
時期に関係なく、「御仏前」「御佛前」
浄土真宗では亡くなったらすぐに仏になるという「即身成仏」の考え方から「御霊前」は使用しません。
神式
「御神前」「御玉串料」「御榊料」
キリスト教(カトリック)
「御ミサ料」「御花料」「御霊前」
キリスト教(プロテスタント)
「御花料」「献花料」「弔慰料」
プロテスタントの場合「御霊前」「御香典」は使用しません。
無宗教や宗教宗派が分からない時
無宗教の場合には「御香典」を使用するのが最も無難です。
宗教宗派が分からない場合には、「御香典」「御霊前」を使用します。
使ってはいけない宗教宗派もあるので、分からない場合のみとしましょう。
不祝儀袋の選び方
宗教や宗派によって、選ぶ不祝儀袋にも決まりがあります。
地域によって多少の違いはありますが、基本的なマナーを知っておきましょう。
仏式
水引が黒白か双銀の結びきり
浄土真宗
水引が黒白、双銀、藍銀の結びきり
神式
水引が黒白、双銀、双白の結びきり
キリスト教(カトリック、プロテスタント)
水引がなく、十字架模様やユリの花がプリントされたものか、郵便番号枠のついていない無地の白封筒
無宗教や宗教宗派が分からない時
無宗教か宗教宗派が分からない場合には、白無地の封筒を使用しましょう。
不祝儀袋の名前の書き方
表書きの下には持参した人の名前を記入します。
一人の場合は中央にフルネームを書けばよいですが、連名などの場合にはどうしたらいいでしょうか。
いくつかのパターンについて見ていきましょう。
2名の場合
中央に代表者や目上の人、その左にもう一人の名前を書きます。
夫婦の場合は中央に夫、左側に苗字を省略した妻の名前を書きましょう。
妻が夫の代理で持参した場合は中央に夫の名前を書き、その下に小さく「内」と書いておくとわかりやすいです。
3名の場合
中央に代表者や目上の人、左にいくにしたがって目下の人の名前を書きます。
上下関係がない場合は五十音順で問題ありません。
4名以上の場合
中央に代表者の氏名、右側に団体名や会社名、左側に他一同か他〇名と記載し、白い無地の便せんに全員の氏名、住所、金額を書いて不祝儀袋の中に入れておきます。
中袋の書き方とお金の入れ方
中袋とは、不祝儀袋の中にお金を入れるための、白い封筒の事です。
通常はセットになっています。
こちらにも書き方に決まりがありますので、詳しく見ていきましょう。
表面の書き方
金額を縦書きで書きます。
「金参仟圓也」「金伍萬圓也」など、旧漢字を使用します。
旧漢字は二なら「弐」、三なら「参」、五なら「伍」、十なら「拾」です。
裏面の書き方
裏面には、郵便番号、住所、氏名を縦書きで書きます。
お金の入れ方とマナー
次にお札を入れる際のマナーや注意点についてご紹介します。
新札は使用しない
お金を入れる時に、新札は使用しないようにしましょう。
どうしても新札しかない場合は、軽く2つに折って折り目をつけて入れます。
お札の向き
まず封筒にお金を裏返して入れます。
できれば人物側を下にします。お金を入れたら封をせずに外袋に入れます。
外袋は上側をかぶせるようにしましょう。
香典を渡す時のマナー
しっかりと準備をしていっても、いざ渡す時にマナー違反をしてしまうと元も子もありません。
ご遺族のお気持ちを考え、落ち着いてお渡ししましょう。
この項目では、斎場で実際にお渡しする際のマナーについて説明していきます。
袱紗を使用する
用意した不祝儀袋は、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。
袱紗の色は、グレー、紫、藍などですが、紫は慶事用にも使えますので一つは持っていると良いでしょう。100円ショップなどでも買えます。
包む際は、袱紗を広げて少し右寄りに不祝儀袋を置き、右、下、上、左の順に布を折ります。(慶事では逆になります。)
最近では簡易型の袋状タイプのものもありますので、その場合はそのまま入れましょう。
挨拶の言葉をそえて渡す
袱紗に包んだ不祝儀袋は、直前で袋から出します。
右手にのせて左手で布をめくり取り出して、両手で相手に名前が見えるよう、向きを変えてお渡しします。その際、無言ではなく挨拶のひとことを添えましょう。
宗教・宗派ごとに挨拶の例をご紹介します。
仏式
「この度はまことにご愁傷様でございました。どうぞ御霊前(御仏前)にお供えください」
「この度はお気の毒さまでございました。どうぞ御霊前(御仏前)にお供えください」
※浄土真宗の場合「御仏前」
神式
「御霊(みたま)のご平安をお祈りいたします」
「心より拝礼させていただきます」
キリスト教
「〇〇さまが安らかに眠られますようお祈りいたします」
「お知らせ頂きありがとうございます。安らかなお眠りをお祈りいたします」
※キリスト教では「ご愁傷さま」という言葉は使用しません。
まとめ
ご葬儀に参列する際、突然のことで気持ちが落ち着かないまま参列することも多いのではないでしょうか。
ですがご遺族も悲しみの中でご葬儀をされていますし、最大限の心配りが必要です。
表書きの書き方、お金の入れ方、渡し方など失礼にならないよう、落ち着いて準備して参列しましょう。